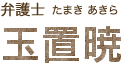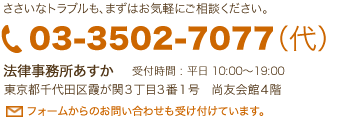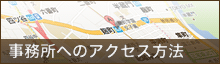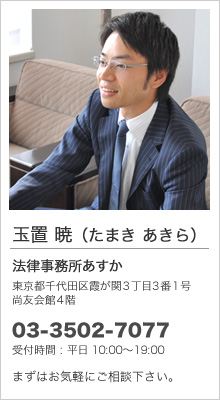「相続」に関連する法律・判例情報
アメリカの相続制度と信託
アメリカの相続制度と信託
アメリカでは、相続の制度が日本と異なります。
日本では、被相続人の死亡と同時に相続が発生し、遺言書がない場合、相続財産(遺産)は、プラス(資産)もマイナス(債務)も含め、原則として相続人の共有財産となり、相続税は相続人が納付することになります。
これに対して、アメリカでは、州によって手続や相続人の範囲等で差異があるものの、基本的に、被相続人の死亡によって相続は開始せず、裁判所の管理下において、プロベート(Probate)と呼ばれる公的な手続(検認裁判とも呼ばれます。)によって、資産と債務の清算が行われ、遺産税(Federal Tax, State Tax)を納めたうえで、残った財産が相続人に分配されることになります。
この手続は煩雑であり、時間もかかります。
遺言書を作成することによって、時間的・費用的な負担を減らすことはできますが、遺言書のみでは、プロベートを回避することはできません。
そこで、生前信託の方法が有用とされています。

共同相続人間の遺留分減殺請求
複数の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言により、一人又は一部の相続人の遺留分が侵害された場合、その遺留分を侵害された相続人が行使する遺留分減殺請求の対象は、他の相続人に対する遺贈又は相続させる旨の遺言の目的物の価額のうち、遺留分を超える部分のみ、です。
(最高裁判決平成10年2月26日)
つまり、遺留分に満たない価額の財産のみ遺贈を受けた相続人は、遺留分侵害請求の対象とはなりません。

住所のみにより特定された「不動産」の遺贈の対象
住所のみにより特定された「不動産」の遺贈の対象
遺言には、いわゆる住居表示(住所)が記載され、その「不動産」を「Xに遺贈する」とされていた。
その住居表示(住所)は、土地の地番や建物の家屋番号とは異なる。
当該遺言における「不動産」が「建物」のみを意味するのか、「土地及び建物」の両者を意味するのか、という解釈について、相続人間で争いになった。

第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力
第一相続人に姪を指定する旨の遺言の効力
遺言書において、
「第一相続人A(姪)を指定 第二相続人B(Aとは別の姪)を指定」
「家の再こうをお願いします」
といった記載があった。
なお、遺言者は、Aとの養子縁組を希望しており、遺言書の前後から死亡の直前に至るまで、数度にわたり、Aとの養子縁組ついてAに打診したが、Aに拒否され、成立しなかった。
また、Bとの養子縁組についても、交渉があったが、実現しなかった。
Aは、「第一相続人Aを指定」の文言は、Aにすべての遺産を遺贈する趣旨であると主張した。

「相続させる」旨の遺言によって遺産を取得することとされた相続人が遺言者より先に死亡した場合(代襲相続の可否)
相続人Aに不動産・預貯金等を「相続させる」との遺言が作成された後、被相続人(遺言者)より先に相続人Aが死亡した場合、相続人Aの子Bは、上記「相続させる」遺言(遺産分割方法の指定)を代襲相続するでしょうか。

遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か
遺言執行者に受遺者の選定を委ねる遺言は有効か
遺言執行者を指定し、なおかつ、「遺産の全部を公共に寄与する。」との趣旨の記載のある遺言は、どのように解釈すべきでしょうか。

共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は有効か
「財産の分配は、長男Aに一任する。」という内容の遺言について、長男に対し、他の共同相続人が遺言無効確認の訴えを起こしました。
上記のように、共同相続人の一人に財産の分配方法を一任する内容の遺言は、有効でしょうか。