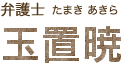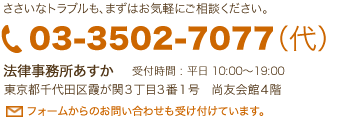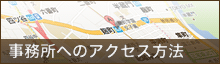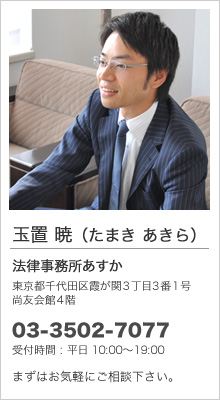「相続」に関連する法律・判例情報
受遺者が取得する財産の価額の決定を遺言執行者に委ねる遺言は有効か
要旨、「Aに3000万円から5000万円を相続させ、BとCには、特定の不動産と金銭を遺贈する。それぞれの取得額の決定を遺言執行者(弁護士)に委ねる。」との遺言は、有効となるでしょうか。

遺留分減殺の方法・順序について
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象となるのは、①遺贈、②相続開始前1年間になされた贈与、③遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与、④不相当な対価をもってした有償行為及び⑤相続人に対する特別受益などです。

遺留分減殺請求をしてはならないことを遺言書で定めた場合の効力
「遺留分減殺請求をしないこと」「遺留分減殺請求をしてはならない」などと遺言書で定めても、法的な効力は生じません。
ただし、遺留分減殺請求を行使しないように求める遺留分権利者が納得できるような理由を付記したうえで、遺留分権利者による遺留分減殺請求の行使を(任意に)思いとどまらせるため、上記のように記載することそれ自体は禁止されていません。

推定相続人が遺言者より前に死亡した場合の遺言書の効力
事例
1 B及びXは、いずれもAの子であり、YらはいずれもBの子である。
2 Aは、平成5年2月17日、Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条からなる公正証書遺言をした。本件遺言は、Aの遺産全部をBに単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定するもので、当該遺産がAの死亡の時に直ちに相続によりBに承継される効力を有するものである。
3 Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡した。
4 XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Yら=Bの子=Aの代襲相続人らに対し、Aがその死亡時に持分を有していた不動産につきXが法定相続分に相当する持分を有することの確認訴訟を提起した。
Xの請求は認められるか?/それとも、Yらの代襲相続は認められるか?

遺産の評価時期(遺産評価の基準時)、特別受益の評価の基準時、遺留分算定の基礎財産の基準時
1 遺産の評価時期(遺産評価の基準時)
遺産を具体的に分配する際の財産の評価は、遺産分割時を基準とします。
つまり、相続開始から、遺産分割までの間に、遺産を構成する財産の価値(時価)に 変動があった場合には、具体的に遺産分割をする時点の価値で、分配することになります。

遺産を確保(保全)する方法
遺産分割協議が成立(終了)する前に、特定の相続人によって遺産が処分され、消失してしまうと、他の相続人の権利が害され、また、協議も無駄となってしまい、取り返しのつかないことになりかねません。
では、そのような事態を避けるため、遺産の消失を防止するには、どのような方法があるでしょうか。

寄与分の具体的な計算方法
遺産分割の際には、どうやって計算するのか?
・まず、「寄与分」を相続財産からマイナスします。このマイナスした後の財産を「みなし相続財産」と言います。
・次に、「みなし相続財産」を基礎に、各相続人の相続分を算定します。遺言で相続分の指定がなければ、法定相続分で割ることになります。
・最後に、寄与者だけ、「寄与分」の分を自己の相続分にプラスします。
では、具体例を見てみましょう。

寄与分
「寄与分」とは何か?
相続人の中に、被相続人(の財産)に対して特別の貢献(寄与)をした人(「寄与者」と言います)がいた場合に、それをまったく考慮せずに遺産を分けると相続人間で不公平が生じます。
そこで、民法は、遺産分割の際にその特別の貢献を考慮し、清算する制度を規定しました。
簡単に言うと、特別の貢献の分だけ遺産を多く分けてもらえるという制度で、その多くもらえる分を「寄与分」と言います。