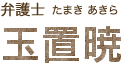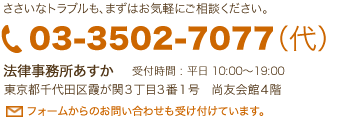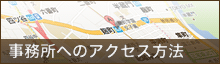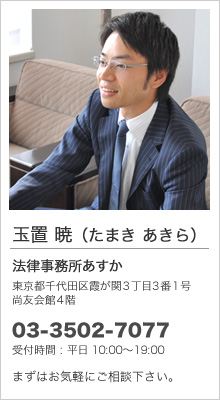「制度説明」に関連する法律・判例情報
アメリカの相続制度と信託
アメリカの相続制度と信託
アメリカでは、相続の制度が日本と異なります。
日本では、被相続人の死亡と同時に相続が発生し、遺言書がない場合、相続財産(遺産)は、プラス(資産)もマイナス(債務)も含め、原則として相続人の共有財産となり、相続税は相続人が納付することになります。
これに対して、アメリカでは、州によって手続や相続人の範囲等で差異があるものの、基本的に、被相続人の死亡によって相続は開始せず、裁判所の管理下において、プロベート(Probate)と呼ばれる公的な手続(検認裁判とも呼ばれます。)によって、資産と債務の清算が行われ、遺産税(Federal Tax, State Tax)を納めたうえで、残った財産が相続人に分配されることになります。
この手続は煩雑であり、時間もかかります。
遺言書を作成することによって、時間的・費用的な負担を減らすことはできますが、遺言書のみでは、プロベートを回避することはできません。
そこで、生前信託の方法が有用とされています。

所有者(個人)が代表者である法人が競売物件を占有している場合の引渡命令の可否
まず、抵当権を実行された競売物件の所有者が当該物件を占有している場合、当然に、引渡命令の対象となります。
※引渡命令に関する解説はこちら。
それでは、競売物件の所有者が個人であった場合において、その所有者が代表者となっている法人が占有している場合、引渡命令の対象となるでしょうか。

遺留分減殺の方法・順序について
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象となるのは、①遺贈、②相続開始前1年間になされた贈与、③遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与、④不相当な対価をもってした有償行為及び⑤相続人に対する特別受益などです。

遺留分減殺請求をしてはならないことを遺言書で定めた場合の効力
「遺留分減殺請求をしないこと」「遺留分減殺請求をしてはならない」などと遺言書で定めても、法的な効力は生じません。
ただし、遺留分減殺請求を行使しないように求める遺留分権利者が納得できるような理由を付記したうえで、遺留分権利者による遺留分減殺請求の行使を(任意に)思いとどまらせるため、上記のように記載することそれ自体は禁止されていません。

遺産の評価時期(遺産評価の基準時)、特別受益の評価の基準時、遺留分算定の基礎財産の基準時
1 遺産の評価時期(遺産評価の基準時)
遺産を具体的に分配する際の財産の評価は、遺産分割時を基準とします。
つまり、相続開始から、遺産分割までの間に、遺産を構成する財産の価値(時価)に 変動があった場合には、具体的に遺産分割をする時点の価値で、分配することになります。

寄与分
「寄与分」とは何か?
相続人の中に、被相続人(の財産)に対して特別の貢献(寄与)をした人(「寄与者」と言います)がいた場合に、それをまったく考慮せずに遺産を分けると相続人間で不公平が生じます。
そこで、民法は、遺産分割の際にその特別の貢献を考慮し、清算する制度を規定しました。
簡単に言うと、特別の貢献の分だけ遺産を多く分けてもらえるという制度で、その多くもらえる分を「寄与分」と言います。